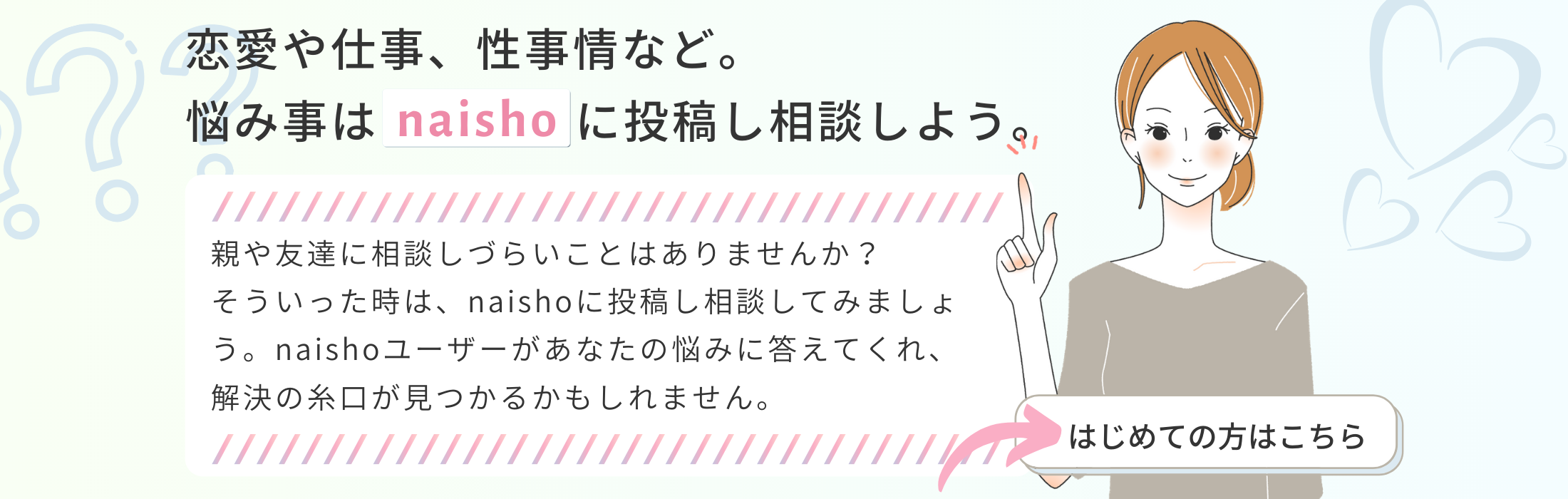「自殺するときはマンション以外にしてね。違約金がかかるから」
「そんな顔で、生きていて恥ずかしくないの?」
「貴女は頭がおかしい病気なのよ。だから幸せにはなれない」
「貴女なんて産まなければ良かった」
私は母を、恨んでいた。
醜い容姿に産んだこと、思い通りに育たない私に暴言を吐き続けたこと。
専門学校の実習着を水浸しにされたり、奨学金を使い込まれたこと。
母が私の存在を否定するのと同じくらい、私は母の存在を、「赤の他人」として扱ってきた。
あるとき、友人に言われたことがある。
「yuzukaってさ、親が死んだら、悲しいって思うの?」
少し考えたあと、「思わない」って答えたあの言葉は、今でも間違いではないと思う。
よく、他媒体のコラムなんかで「親を愛さなくても良いよ」って内容のものをアップする度、
「なんだかんだ言ったって、血が繋がっているから愛し合っているんだよ」なんて能天気な言葉が飛んで来るが、
この際だから、はっきりと否定したい。
血の繋がり?んなもんは、相互フォロー以下の重みしかもたねえよ。
断言する。
子を愛さない親は、存在する。それも、少なくはない。
それを認められないのは一部の恵まれた人たちだけだという事実をちょっと飲み込んでほしくって、この記事を書く。
目次
私の家庭
私の弟は、高次脳機能発達障害だった。
中学生の頃引きこもりになった彼は、自室に鍵をつけ、一日中大爆音でネットに転がっている
悪魔からのお告げを聴き続けた。
今思えば、あの頃の彼はうつ病やその他合併症を併発していたのだと思う。
見た目は至って普通で、会話もできる。なんの知識もない人間からすれば、怠けているだけに見えた。
「鬱は水をかければ治る」という典型的昭和根性脳の父親がいることもあって、
発達障害であるという認識すら持たれずに引きこもり扱いされる彼自身も、かなり辛い日々を過ごしていたのではないかと、今となっては予想する。(彼に診断名がついたのは、もっともっと後の話)
ただし、その頃の私は、今の私とは違う。
基礎看護技術でシーツ交換の仕方を習ったばかりの高校1年生。
今でこそ精神科の知識を持っているが、その頃の私は、勿論ただのJK。
私の目に映る弟は、狂人そのものだった。
家の包丁が消え、横の部屋からは爆音の悪魔のお告げと、壁を殴る音が聞こえてくる。
中学校のプールに墨汁を流し込み、賠償金を請求されたこともあった。
奇行を目の当たりにする度、毎日毎日、「いつ刺されるだろう」という恐怖に怯えていた。
一方で私はと言えば、所謂リア充。友達もそこそこ多い、一般的な高校生。
地元の友達から弟のせいで白い目を向けられるのが怖かった私は、弟とは距離を置き、一切の関わりを持たなかった。
そしてこの辺りから、母親が狂っていくことになる。
弟の機嫌を損ねるのが怖いから、毎日指定されたご飯を、鍵のかかった部屋の前に置いた。
なぜか彼の奇行の原因は私であると認識し、私を攻撃するようになる。
攻撃といっても些細なことだ。
食事を与えないとか、暴言を吐くとか、勉強中にブレーカーを落としてくるとか、その程度。
だけど家に帰る度にそういう行為を喰らうわけだから、私もだんだん、家に寄り付かなくなった。
寄り付かなくなったらなったで、すぐに警察に捜索願を出されて逆探知からの実家へ連行されるので、あまり意味はなかったのだけれど。
とにもかくにも実家が嫌で仕方なかったある日、私が弟に、顔面を思いっきり蹴り上げられるという事件が起きた。
鼻の付け根をいかれたもんだから、私の両目の下(ちょうどクマができる場所の下あたり)には
真っ青な痣ができた。
その時に母が発した言葉を、今でも忘れられない。
鼻血を流して泣く私を床に突き飛ばし、弟を抱きしめながらこちらを睨んでひとこと
「いい加減にしてよ!この子がやったと思われたらどうするの!自分でやったって言いなさいよね!」と、言った。
親との絶縁
いろいろとエピソードはあるけれど、不幸自慢になりそうなので、いくつか主要な出来事を。
(1)私の奨学金は、弟のハーレーを買うために使い込まれてしまう。
(2)それも底を尽きて弟のために借金を繰り返した母親はパンク、自殺未遂。母親が自己破産をすると実家ごと差し押さえられ、二世帯で住む祖父母の家がなくなるので、私が肩代わり。なんだかんだで風俗デビュー。
(3)弟が新興宗教の信者になる。
と、いろいろな出来事がありつつ、それでもちょくちょく連絡は取っていたのだが、
上京後のとある出来事で、私の堪忍袋の尾が切れた。
急性腎炎で倒れて救急車を呼ぼうにも手持ちのお金がなかった私が、生まれて初めて母親を頼って電話をすると
「お金がないなら諦めて死ぬしかないんじゃない?」と受話器を降ろされたのだ。
ショックとか、怒りとか、そんな感情すら湧いてはこなかった。
ただ、冷や汗が止まらないまま、結局風俗客に電話をしてお金をせびる自分自身を客観的に眺めながら、
「惨めだな」って、それだけ思った。
私はそのすぐ後、親と絶縁した。
それから数年間風俗で働きながらだらだらと生活していく中で、親の顔が浮かんだことなんて、ほとんどなかった。
それと同じく、親から暴言以外の連絡が来ることも、なかった。
母親の手料理を食べたことなんて数回だけだし、家族揃って食事をして笑い合うなんて、
ほんの幼少期にあったかどうかわからない程度の記憶だし。
私にとってテレビにうつる「家族」ってのはバーチャルで、恵まれた人たちが持っている贅沢品で、
私はたまたまそれを持っていなかったってだけ。
時々、「風俗で働くくらいなら、親に頭を下げて、お金を借りれば良いじゃない」と言ってくる客がいた。
「親のせいで風俗で働いているんだよ」って答えたら苦笑いをしていたけれど、
彼は「親子の絆」ってものが、何にも邪魔をされない、誰にとってもすばらしいものだと信じていたのだろう。
ちょっとディズニーの見過ぎじゃない?
どうして私だけ「普通の家族」が与えられなかったのだろう。
前世で何かしたのかなあ。こんな私が、幸せになれるわけなんてないよなあ。
母に、「あんたみたいなブスが幸せになれるはずがないから、早めに死になさい」とか
「絶対に子孫を残すなよ」と言われる度、「そうだよなあ」って、おぼろげに思っていた。
いくらGoogleカレンダーをめくっても、私が幸せになる予定なんて、なかった。
お墨付きの「不幸な人生」。私はずっと、このレールを歩いて行くのだと思っていた。
本を出す
さて、そんな私が本を出すことになった。
人生というのは、何があるか分からないものだ。
看護師として注射器を握っていた私が風俗嬢としてちんこを握り、そして最後には、ライターとして筆を握っている。
本のテーマはいろいろあったけれど、だけどとにかく「あの頃の私」にかけたい言葉を書こう。と、決めていた。
風俗を始めた頃の私。仕事に行きたくなくて泣いていた私。シャワーの中で、何度もなんども身体中を洗っていた私。
涙もうまく流せなかった、「あの頃の私」。
ひとりぼっちの「あの頃の私」を、どこかに置き去りにしてきているような気がして。
だけど、四苦八苦してようやく書き上げた本を何度読み返しても、「あの頃の私」がどんな「私」だったのか、ちっとも浮かんでこなかった。
そして、何か得体の知れないわだかまりが、心の中でモヤモヤと膨らんでいった。
「この気持ちの正体は、なんだろう。きっと、あの頃の私に会ってみないと分からない。」
分からないから、会いに行く。会いに、行ってきた。
yuzuka
最新記事 by yuzuka (全て見る)
- イスラエル初の美顔器『トライポーラ STOPV』を試してみた!実践レビュー【PR】 - 2021年1月18日
- 男性に生理を管理され、とても気持ち悪いと思った本音 - 2020年10月21日
- ずっと変わることのない卵とじうどん - 2020年10月20日