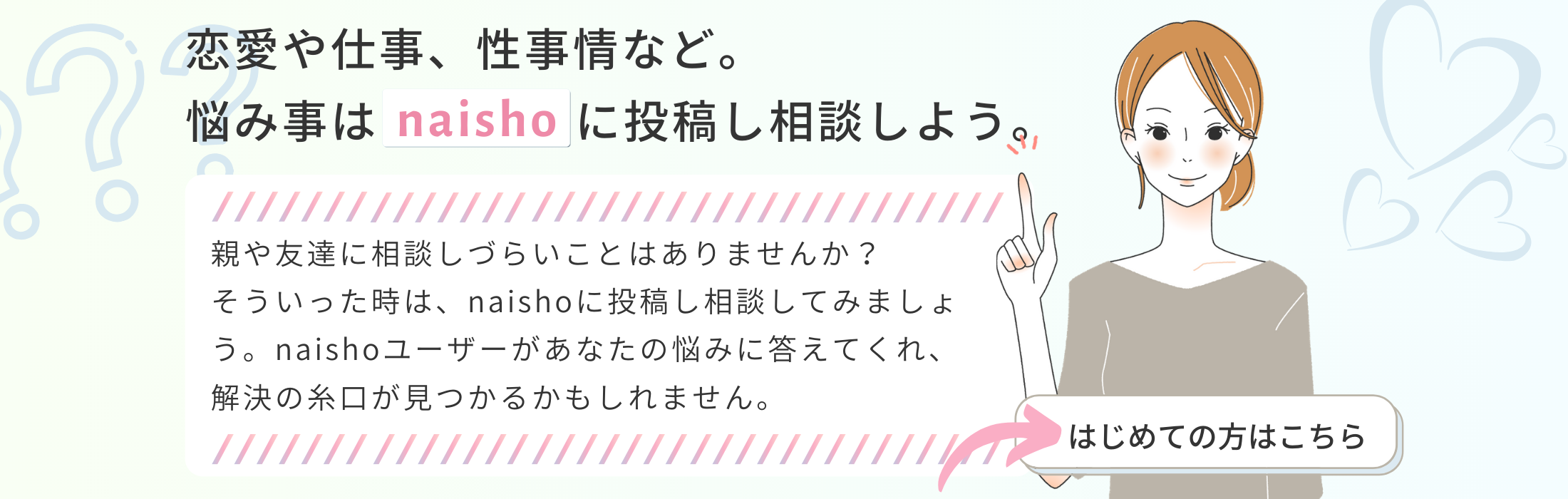新型コロナウイルスは、突然姿を現して、
その毒は徐々に世の中にはびこって、あっというまに侵食した。
最初はマスクを買い求める人を「大げさだ」とばかにしていた友人も、
いつしか政府に配られたマスクや割高で購入した消毒液を持ち歩き、リモートワークを強いられて、
明言された自粛期間を終えた今だって、いまだに人々の数はまばらだ。
だけど本当の闇は、散々バカにされたあの政府のマスク二枚すら届かなかった人たちにこそあったと思う。
住民票を持たずに、ネットカフェに暮らす人々がいる。
彼らの「家」は営業自粛に追い込まれ、そこに暮らしていた人たちは皆、立ち退きを強いられた。
かつてそこで暮らしていた3349人の人たちの行方を、私たちは知らない。
コロナウイルスの流行がいよいよ深刻になりはじめた頃、「それでもお金がないから、子どものためには働かなくちゃいけないの」と
感染の恐怖と戦いながら風俗店に出勤していた私の友人の働く店もまた、営業自粛となり、未だに再開していない。
変わらずに営業を続けていたお店もあったにはたけれど、客足は遠のき、普段数ヶ月先まで予約でうまる女の子が、一円も稼がずに家に帰る状況が続いていたりする。
こんな状況で、働ける店がない。
ようやく見つけてそこで働いたとしても、稼げない。
それどころかもしもその店で感染してしまったら、全国から石を投げられて見世物にされることを、彼女たちは知っている。
だけどそれじゃあ、どうしたら良いのだろうか。
彼女たちの多くは住民票を持たず、その日暮らしで生活している。
政府から配られる名ばかりの給付金すら、受け取れないであろう人たちの顔が、たくさん浮かんでくる。
明日電気が止まるのを防ぐために、今日1万円を稼ぐ。
今日変えるオムツを買うために、数千円を稼ぐ。
そんな彼女たちが突然働く場所を失い、そしてなんの保証も受けられない、制度の隙間におっこちている。
彼女たちの行方も、今後についても、誰も知らないし、 考えない。
「自業自得」
そういってほくそ笑んで無視する彼らもきっと、貧困をテーマにした映画を見て泣いたりはするのだろう。
現実世界で食事を乞うホームレスを無視するのも、ふかふかの観客席に座って感動の涙を流すのも、簡単で、その場限りで、どうだって良い。
目次
風俗嬢のティアラちゃん
「ねえ、桃ちゃん、手伝って」
ティアラちゃんはそう言って、私を待機室の奥のトイレに呼びつけた。
私たちはお互い、本名を知らないし、聞かない。
風俗嬢の世界でそれは常識で、マナーだ。
21歳なのに中学生のブルマのコスプレを着させられていた私は、
呼ばれるがまま彼女のいるトイレに入った。
すでに水が流れた後の大きい流水音がするその部屋で、その音にまぎれそうなくらい
小さな声で、「シャブ、トイレに流してるねん」と、彼女はそう言った。
風俗店の待機室はワンルームマンションをそのまま使っていることが多く、
そこはユニットバス式のトイレで、トイレの横には浴槽があり、
その中にイソジンやローションの詰め替え用パックが大量に押し込まれていた。
その詰め替え用パックの山の上に無造作に置かれた、
ルイヴィトンの主張が激しい大きな手提げ鞄の中に、小さなジップロックに白い粉を入れた何かが
溢れんばかりに詰め込まれている。
「パケ。彼氏から、処分しろって言われてんねん。シャブやで。欲しい?」
彼女はいたずらに笑った後、冗談やってと軽口を叩いてから、大量の「パケ」の中のうちの
ひとつを指先でつまみ、天井に向かって持ち上げながら眺めた。
「これ使ってるときだけ、全部忘れられんねんけどなあ」
ティアラちゃんには3人の子どもがいて、彼氏は暴力団の下っ端で、団地に住んでいる。
背が高いのに体重は150cmの私と同じくらいしかなくて、カラコンはドンキホーテのシルバー。
1日使い捨てカラコンを、2ヶ月使う。
私の知っている情報は、それくらいだ。
その店では最年長の実年齢42歳だった彼女はいつもセーラー服を着ていて、私たちと同じく、体を売って稼いでいた。
ブサイクだろうがデブだろうが、若い女だということに一番需要があるその業界で、
綺麗だけど年季の入った妊娠線とリストカットがあり、40代だという噂がある彼女の人気は、低かった。
その証拠に、一日中働いた夜中、なんの稼ぎも得られずに家に帰る彼女を、なんども見たことがある。
「なあ、電気代と水道代貸してくれへん?止まってもて、子どもが暑そうやねん」
ある日の閉店後、給料の受け取りを済ませて身体中にボディークリームを塗りたくっていた。
私のそばに来た彼女はそういって、机の上に出しっぱなしにしていた私のその日の給与明細に視線をおろした。
その日、彼女がこの店で唯一ひとりもお客さんがつかなかったことを知っていた私は、
妙な罪悪感から断ることができなくて、一万円札を手渡した。
「ありがとうな」
彼女はそう言って、制服姿にパーカーをはおり、そのまま出口に向かって歩いていく。
「そのままの格好で帰るん?」
驚いて問いかける私に彼女は綺麗な顔でニッカリ笑いかけて、何も言わずに、右手をあげた。
それが私の見た、彼女の最後の姿だった。
ある夏の日、ティアラちゃんはあっけらかんとその店から姿を消し、そのまま帰らなかった。
彼女の子どもはどうなったのか、電気代は払えたのか、そんなことももう、分からない。
もっとハードプレイが求められるお店に移店したらしいとか、薬漬けになって捕まったらしいとか
一家心中したらしいとか、そんな噂を何度か聞いたけど、その真偽は分からない。
社会の制度から外れた私たち
ちょっとしたきっかけで社会の制度から外れた私たちは、「普通の世界」では誰からも、話を聞いてもらえなくなる。
「自己責任」「税金も払ってないくせに」「自業自得だ」
社会から向けられる冷たい目を避けるうちに同じような人間で構成された場所にたどり着くと、
ぬるま湯につかったときのように、全身がその場に溶け込んでいく。
そこには堕落した自由があり、話す人がいて、
現実逃避のためのありろあらゆるものがはびこっている。
薬物や酒、消費、セックス。
そういう環境に身を投じているうちにやがて人生を、諦めるのだ。
誰もが細い、今にも切れそうな綱の上を慎重に歩いている。
ほんの少しの何か小さなきっかけで、その紐はいとも簡単にちぎれて、真っ逆さまに落下する。
その先のことは、誰もしらない。
数年前に私がいた世界は、そんな世界だった。
誰にでもその可能性が潜んでいる
誰もが細い、今にも切れそうな綱の上を慎重に歩いている。
ほんの少しの何か小さなきっかけで、その紐はいとも簡単にちぎれて、真っ逆さまに落下する。
それは、画面の前にすわっているあなたも、同じだ。
極地にたっている彼女たちのことを「自業自得」だとあざ笑う人がいる。
永遠に交わることのない遠い世界の不幸な人たちとして、鼻で笑いながら見物している人たちがいる。
だけど本当のところ、彼女たちはあなたと同じ人間で、あなたと違う部分はたったひとつ、人生を狂わせる「きっかけ」に出会ってしまったか、出会わなかったか。
それだけなのだ。
ティアラちゃんはが生きていたら、彼女は今、50歳だ。
本名を聞けばよかった。
そんな後悔をしながら、私は今も記憶の奥にある彼女のにかっと笑った笑顔が、この世界のどこかに存在していることを、
こっそりと願っている。
yuzuka
yuzuka
最新記事 by yuzuka (全て見る)
- イスラエル初の美顔器『トライポーラ STOPV』を試してみた!実践レビュー【PR】 - 2021年1月18日
- 男性に生理を管理され、とても気持ち悪いと思った本音 - 2020年10月21日
- ずっと変わることのない卵とじうどん - 2020年10月20日