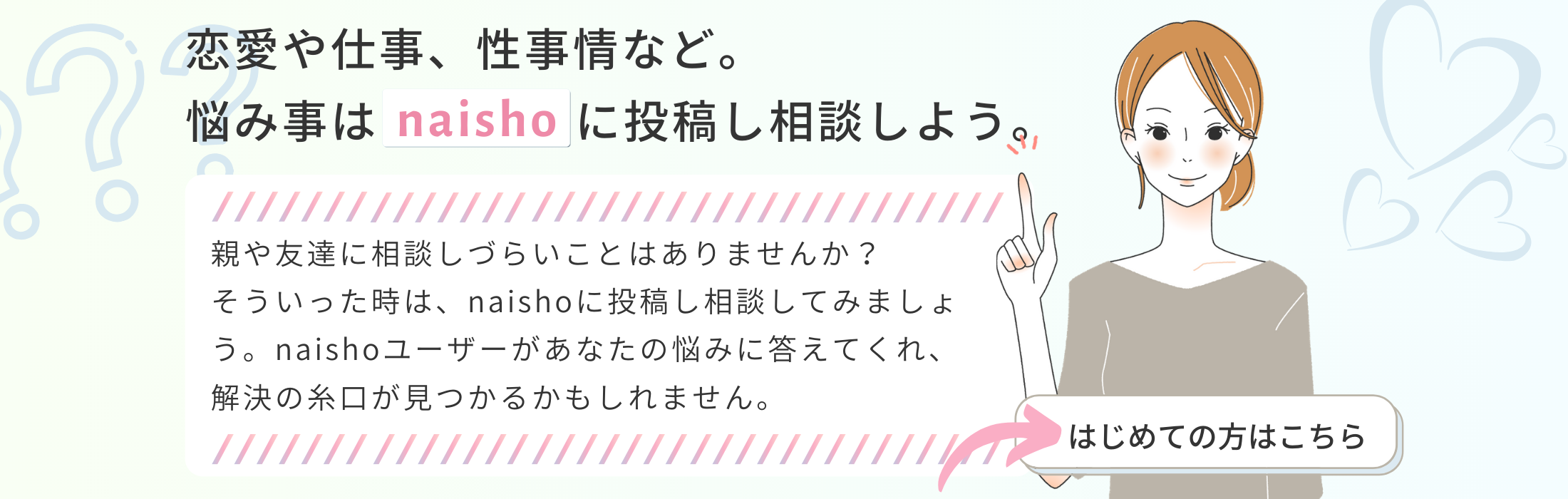はじめまして。警察学校を3日で脱走した男、浜渡浩満(@_neetkun)です。
僕はこれまで50以上の仕事をバックレたり、警察学校を3日目の夜に脱走したりと逃げ続ける人生を送ってきた。
こんな僕が初めてバックレをし、逃走人生の幕を開けた最初のバイトは、
チェーン居酒屋のバイトだった。
居酒屋バイトと言えば、大学生バイトの花形。
大学のキャンパスで女の子と仲良くなることに失敗していた僕は、可愛い女の子との出会いを密かに期待し、華やかなバイト充な生活を心のキャンバスに描いていた。
個人経営ではなくチェーンの居酒屋にしたのは、単に時給が高かったのと、チェーンの方が人が多い、すなわち女の子との出会いも多いだろうと思ったからだ。
オブラートよりも極薄の動機で応募した僕は、居酒屋のオープニングスタッフとしてキッチンで初バイトをすることになった。
そして結論から言うと、僕は全く仕事ができなかったのだ。
今でこそ自分に注意欠陥障害があると分かっているから納得だが、当時は大きな挫折を味わった。
そんなダメダメだった居酒屋バイトで懸命にもがいた結果、心が複雑骨折してしまい、完治はしたものの元の自分とは全く別の姿になってしまった。
この話はそんな話になる。
勤務初日、いきなり遅刻してしまった僕は、焦りから視界が霞んで、入口に迎えに来てくれた店長本人ではなく鏡に映った店長に謝った。
怒られることも笑われることもなく、居酒屋バイトはぬるっと幕を開けたのだ。
チェーン居酒屋のキッチンは大体どこも同じだと思うけれど、 揚げ場→調理場(チャーハンを作ったりする等フライパンを使う所)→焼場→刺場(刺し身やサ ラダ)の順に覚えていく。
ただ僕の場合は、あまりにも仕事覚えが遅く、さらにすぐテンパってミスをやらかし続けたこともあり、半年間で調理場の導入作業までしか到達しなかった。
そして本来の目的であった女の子との宝石のようなキラキラした生活などなく、キッチンは僕以外全員一緒に応募してきた元ホストという状況で、ひたすら弄られ石ころのように扱われた。
ダイヤの原石ならその内輝き出すことができたのだろうか。
路傍の石ころの僕は、徐々にすり減っていき、角が取れて丸い石ころになっていくのみだった。
もちろんホールの方には女の子もいたけれど、対人恐怖症を発揮したのと、仕事が全くできない負い目から全然仲良くなることはできなかった。
本末が転倒しているけれど、仕事に必死でそんなことに構ってられなかったのもある。
地雷よりもタチが悪い。
誰かがプレッシャーをかけなくてもそこら中で爆発を繰り返し、キッチンを荒らして回ったのだ。
数えきれないほどの痛恨のやらかしをした。
揚げ餅を爆発させた挙げ句、びっくりして油の入った缶をひっくり返し、キッチン中を油まみれにしたこともあった。(その後、ヤクザみたいな店長はブチ切れ、僕の首根っこをつかみ、壁に押し付けた。恐いし痛かった...)
僕がシフトに入るとしばしばキッチンを荒らし、結果、料理の提供に大幅な遅れが出てクレームだらけになる。
その崩壊した状態のことを、店長は「ヤラレる」と名付けたのだ。
ある日店長と2人だけのシフトがあった。
店長が「もし今日ヤラレたら、明日お互い坊主な」と言い、僕は絶対にヤラレる気がしたけれど、多分冗談だろうと思い「分かりました」と答えた。
そして案の定、オーダーの紙が訳の分からないほどに溜まり、もはやどの料理を提供したのかも分からなくなった。
そして僕は、完全にヤラレてしまったのだ。
次の日、出勤すると店長が本当に坊主にしてきた。
僕は頭は丸くしていなかったけれど、目を丸くして店長の頭を見ていた。
「やばい」と思った。
頭は丸めてこなかったけれど、あと何か丸くできるものはないか考え、ひとまず背中を丸めた。
そして、スラムダンクの湘北vs山王工業戦で、桜木花道が「ヤマオーは俺が倒す!」と宣言し、自ら言い訳できない状況を作り出して、宣言通り山王工業を撃破したのを思い出した。
店長は「ヤラレたら坊主にする」という宣言通り坊主にしてきた。 それだけ退路を絶った決意表明の言葉だったのだ。
そんなことを考えていると、店長から当然のように「なんで坊主にしてないんだ」と言われた。
答えられずにいると、首根っこをつかまれ、またもや壁に押し付けられた。
その時このバイトは、僕には無理だと悟り、辞めることを決意した。
その日の営業後、店長に相談して、「今すぐ辞めたい」と言った。
しかし、「すぐに辞めたら履歴書に傷が付くぞ」と脅され、その時はまだバックレをしたことがなかったので、結局大晦日までの年内いっぱいまで働き、その後逃げるように辞めたのだ。
ただバイトを辞めただけ。
今ならそう思えるけれど、当時の僕にとっては大きな挫折だった。
大学入学まで敷かれたレールの上を走り、大人の期待に応える人生を送ってきた。
少し高校の時の話をしたいと思う。
高校では写真部に入りたいと思っていた。
中学の時に読んだ、市川拓司の『恋愛寫眞 もうひとつの物語』という本とその映画に影響されたのもあったし、中学ではバレー部で無理矢理坊主にさせられ、猛烈に厳しい練習をさせられたこともあり、高校では写真部で青春を取り戻そうと思っていた。
しかし、中学の顧問からの圧力と、高校の顧問や先輩からの勧誘に抗うことができず、結局写真部ではなくバレー部に入った。
入ったはまだいいが、高校のバレー部の顧問は中学以上に厳しい人だったのだ。
大学で全国大会優勝した部のキャプテンをしていたということで、当時の厳しい指導を僕らにもしてきた。
僕の高校は進学校だったし、本当は写真部に入りたかった僕は冗談じゃないと思ったけれど、その厳しさは本当に冗談ではなかった。
日常的に体罰を受けたり暴言を吐かれたりは当たり前。 殴られて血を吐いたり、PTSDになる者もいて、裁判沙汰になったりもした。
その鬼顧問は、僕の卒業と同時に別の高校へ異動となり、異動先の高校では自殺者も出たらしい。
他の人はビンタやキックが多かったけれど、僕はガリガリで首が細いからなのか、首根っこをつかまれ壁に押し付けられて、そのまま頭を永遠に壁に叩きつけられるという攻撃をよく受けていた。
そのせいで脳細胞はだいぶ死んだと思う。
また後頭部の絶壁がさらに急な角度になって髪のセットが難しくなってしまった。
そんな常識的な軌道から大きく逸脱した部活だったけれど、辞めることができず、結局、3年間続けた。
レールから外れるということへの強烈な抵抗感が、当時の僕にはあったのだ。
部活を辞めることは別にレールから外れることではないと思うかもしれないけれど、その時の僕にとっては、部活を含め何かを辞めることは、ある種の脱落にも感じられていた。
一刻も早く引退したいと思いながら、我慢の日々を過ごしていたのだ。
それはある面から見れば、文武両道を貫き優等生だったとも取れる。
ただ、別な面から見ると、自分のやりたいことができないボンクラでもあったのだろう。
そんな高校生活を過ごし、大学もその高校で推奨されていた進学率の1番高い大学に入り、まさに筋金入りのレール人間だっただろう。
自分の足で歩くことをせず、皆と同じレールの上に乗せられてきた僕にとって、居酒屋バイトから脱落してしまったのは大きな挫折だった。
周りの人達は居酒屋バイトで10連勤したとか、彼女ができたとか言ってる中、何もできないで辞めてしまうことが、本当に情けなかった。
皆ができている普通ができていない、そんな感覚を初めて味わい、ひどく落ち込んだのだ。
自分が仕事ができない人間だとは、全ったく思っていなかった。
そしてそれから1ヶ月後、何を血迷ったのか、またチェーン居酒屋に応募し働こうとする。
今度はキッチンではなくホールだ。キッチンが駄目ならホールとでも思ったのだろうか。
押して駄目なら引いてみろの理論で、どこにも通じていない扉を開け、また居酒屋バイトを始めた。
店長「浜渡くん、島田紳助って知ってるか?」
僕「ヘキサゴンとか. . .」
店長「いや、今聞いてるのは知ってるかどうかだけだ。答えろ。」
僕「はい、知ってます。」
店長「知ってるんだったら、お前はもっと笑顔で接客しなきゃ駄目だよな。俺もそうだけど、島田紳助みたいに愛嬌のない顔のやつは、普通のやつより笑顔を作らないと駄目だ。」
この人がまたとても怖い店長だった。
僕は対人恐怖症が原因か、笑顔を作るのが相当苦手だった。そのため普段から練習しなければと思い、口角を上げて生活することにした。
すると友達に「どうした、変顔なんかして」と言われ、
鏡を見てみると本当に変な顔だった。
そんなこんなで(どんなどんなだ)、結果から言うと、キッチンよりもホールの方がさらに向いていなかった。
キッチンも全然向いてないのにそれよりも向いてないとなると、もう自分がどこを向いているのかも分からないほどの暗闇の中に入り込んだ気持ちだった。
キッチンよりも細かい作業が多く、さらに接客も加わるので、常に極限の状態まで追い込まれていた。
飲み物はこぼしまくったし、オーダーをうまく取れず、特にドリンクのオーダーが毎回カオスな状況になっていた。
ある日、お通しに小口ねぎを入れ忘れたことがある。それも何度も。
その度店長に「小口ねぎ!」と怒られたけれど、10回以上連続で小口ねぎを入れ忘れてしまい、ついに店長がぶちキレた。
「お前俺を舐めてんのか」と言われ、首をつかまれて壁に押し付けられた。
僕はすみませんと言おうとしたけれど、声にならない声が漏れただけだった。
周りの人達は「わざとやったんでしょ?」と言って爆笑していた。
僕は本気で入れ忘れてしまっていたので全く笑えず、これは絶対に僕にはできない仕事なんだと確信した。
その日、ホールで1番仕事ができる人に「どれくらいで仕事覚えましたか?」と聞くと、「やる気があればこんなん1日で覚えられるよ」と言われた。
僕はその言葉を聞いてさらに望みを絶たれ、辞める決意を固めたのだ。
もう1日たりとも働くことはできないと思った。
ただ前回と同じように辞めることを告げても、「せめて1ヶ月働いてからだ」なんて言われ、ズルズルと辞められないと思ったので、人生初のバックレを決意した 。
次の日、開店前15時くらいのまだ店長しか出勤していない時間を狙い、借りていた物と「辞めます」と書いた置き手紙をキッチンに残した。
そして、僕はそのままバックレた。
これが人生初のバックレだ。
皆と同じ当たり前なことを自分もやれるんだということを、他でもない自分に証明したかったけれど叶わなかった。
自分が他の人とは違う欠陥人間であるという確信を強めた。
レールから外れてしまったという現実から逃れるために、居酒屋が入っていた建物を出ると、そのまま駅に向かい日本三景の一つである松島行きの電車に乗った。
心を燃やし尽くそうとする火急なる現実。
その火から逃れるために非日常に逃げ込む必要があった。
松島に着くと、円通院というお寺の前にあったベンチに座ってがっくりと頭を落とした。
円通院は縁結びで有名なお寺である。そんなお寺の前でこの男はなんで一人で固まってるんだろうと、神様も最初は思っただろう。
だけれども、あまりにも長くうなだれているので、救いの手を差し伸べてくれたのだろうか。
なんとなく気持ちが落ち着いてきた僕は自分の心と向き合い始めた。最初はずっと積み上げてきたものが崩壊したのだと思った。
しかし、何か違和感を感じた。
他人の期待に応えて、周りと同じようにやることを大切にしてきたこれまでの人生に、一体何の意味があったのだろうか。高校の部活も大学すらも周りに流されて決め、本当に自分のやりたいことをやらなかった。
いや、高校の途中からは本当にやりたいことが何なのかを考えることすらやめていた。
レールに乗って順調に進んでいると勘違いしていたけれど、そのレールはどこにも続いていなかったのだ。
当てもなく走る列車に乗って無目的に進んできた僕は空っぽだった。
振り落とされると果てしない荒野が広がっていた。
周りを気にして自分の思う通りに生きてこなかった今までの生き方を、激しく後悔した。
周りと同じようにやることに意味などなかったのだ。
このように考えたのは、欠陥人間である自分を正当化するためでもあったのだろうけれど、
それまで自分の心の奥底に眠っていた真っ赤な本心が、実はそれだったのだ。
その感情は、最初、点のように小さいものだったけれど、それまでの人生で強く圧縮されてきた高密度の感情が一気に心の中に広がっていき、僕の心を赤く染めていった。
そして、それまでの人生全てを否定するに至ったのだ。
自分で選んだ道以外には、何の価値もなかった。そう思った。
それから僕は嫌なことがあるとすぐに逃げるようになった。
嫌なことを続けてもその先には何もないし、周りと同じようにできなくてもいい。
生来の心の弱さも相まってバイトをバックレ続けた。
大学卒業後に入学した警察学校も、3日目の夜にほふく前進等を駆使して脱走した。
誰かの期待に応えるのをやめた所で、自分が無能なことは決して揺るがない。
ここまで極端に方向転換する必要はなかったのかもしれないし、あれ以来あらゆる現実から逃げ続けてきた僕の心は、今でも空っぽのままだ。
どんなに不器用で不格好でも自分で選んで生きていくことを決めた。
何も積み上がってはいないけれど、心に付いた傷の一つ一つこそが、自分の人生を生きてきた証なのだと思える。
浜渡浩満
最新記事 by 浜渡浩満 (全て見る)
- 欠陥人間の僕がはじめてバックレを決めたときの話 - 2019年11月23日